「先生、変なカメムシがいる」と9年生が職員室へ呼びに来てくれました。寒くなると教室へ入ってくるカメムシはいやなにおいを
出すので、だれかが踏んでしまうと大変なのです。でも放送室前の廊下にいたのはこれ、エサキモンキツノカメムシでした。
背中にハートを付けています。次の日のオオムラサキの幼虫探しのときにも見つけてくれました。見つけた人に幸せを運んでくれるかな。
ハートのカメムシ 2011.12.3

ヒメツルソバ 2011.11.9

野村町のマラソンコースで見つけた金平糖のような花は見たことのない種類でした。ミゾソバ(タデ科)の花に似ていて、葉もタデ科らしい形と模様をしています。これはヒマラヤ原産のヒメツルソバだとわかりました。日本へやってきて、野草としてアスファルトのすきまで元気に育っています。
ヤマカガシ 2011.10.13

野村町から集団登校をしている子どもたちが ヤマカカシを運んでいました。道ばたに死んでいたので、 乙が森に持っていってあげるというのです。やさしい気持ちをみんなが持っていて、乙が森にはへびの伝説があることも良く知っているのです。
アサギマダラ 2011.10.12

旅をする蝶アサギマダラが校門にやってきました。ここに植えてあるフジバカマの花に誘われて、蜜を吸いにきたのです。
アサギマダラの追跡調査では移動ルートは沖縄や石垣島からもやってきていることがわかっています。この個体にも 羽根に日付と場所を記入して放しました。
アサギマダラの追跡調査では移動ルートは沖縄や石垣島からもやってきていることがわかっています。この個体にも 羽根に日付と場所を記入して放しました。
テン 2011.10.11

車で通勤される先生から、戸寺の国道そばに倒れているよと教えてもらいました。農業にとってはネズミなどを捕ってくれる有益な動物です。稲荷神社にキツネが祭られているのもそのためです。外傷がないので交通事故ではなく、毒えさを食べたネズミでも食べてしまったのでしょうか。するどい爪をしているので木に登る行動がわかります。
体長40cm、尾長21cm、体重1.6kgのおとうさんでした。
ウスバキトンボ 2011.9.7

学校農園で秋の虫を探し、夏と種類が変わっているのか調べました。イネの上にたくさん飛び回っていたのはウスバキトンボです。
なかなか飛ぶのが速くて 子どもたちが網でとるのは難しいのです。ようやく捕らえて見せてくれました。少なくなったミヤマアカネも見つけることができました。
なかなか飛ぶのが速くて 子どもたちが網でとるのは難しいのです。ようやく捕らえて見せてくれました。少なくなったミヤマアカネも見つけることができました。
何を思うカエルくん 2011.8.22

畑に立ててあった 1mをこえる高い支柱のてっぺんに入って 空をながめていたアマガエルくん。何を思っているのかな。
農薬を使わない畑には カエルが昆虫を求めてたくさん住みついて 活躍していたり、モグラもやってくるのはミミズがたくさんいる
豊かな土になっている証拠です。
農薬を使わない畑には カエルが昆虫を求めてたくさん住みついて 活躍していたり、モグラもやってくるのはミミズがたくさんいる
豊かな土になっている証拠です。
イシガメ 2011.7.8

学校の廊下で歩いていたイシガメです。3年生が捕まえて職員室へ持ってきました。産卵のための場所を探して歩いていたので
しょうか。体重600g 甲長16cmのおかあさんです。昨年、子どもたちに捕まった(2010.5.26)のとは こうらの形が違います。
休み時間に、子どもたちと川へ逃がしに行ってきました。
しょうか。体重600g 甲長16cmのおかあさんです。昨年、子どもたちに捕まった(2010.5.26)のとは こうらの形が違います。
休み時間に、子どもたちと川へ逃がしに行ってきました。
蝶の観察 2011.6.28

子どもたちが保護活動に取り組んでいるオオムラサキです。3年生は観察ノートを持って成虫のようすを観察に行きました。
ものさしで大きさを測っていると、鉛筆などに乗ってきました。指先につけた甘いエサにストローのような口を伸ばしてきます。
ものさしで大きさを測っていると、鉛筆などに乗ってきました。指先につけた甘いエサにストローのような口を伸ばしてきます。
アマガエル 2011.6.24

2年生は教室でアマガエルを飼っています。おなかをすかせたカエルくんのために、モンシロチョウを農園で採ってきたそうです。
食べるかなと みんなで見つめているときはなかなか食べてくれません。
食べるかなと みんなで見つめているときはなかなか食べてくれません。
ウツギ 2011.6.7

和田橋の近くの日当たりのよい川べりに、初夏を飾る白いウツギがたくさん咲いています。ウツギは卯の花とも呼ばれています。
”卯の花のにおう垣根に、ホトトギス 早も来鳴きて. . .”佐々木信綱作詞の「夏は来ぬ」に さわやかな今の季節が歌われています。
”卯の花のにおう垣根に、ホトトギス 早も来鳴きて. . .”佐々木信綱作詞の「夏は来ぬ」に さわやかな今の季節が歌われています。
ヒミズ 2011.5.13

登校中に見つけたと8年生N君が持ってきてくれました。ヒミズはモグラの仲間としては小さめの前足と長いしっぽをしています。
とても小さな目がわかりますか。トンネルは掘らず、落ち葉の下を歩いて昆虫やミミズを食べてます。体長9cm、尾長4cmでした。
写真を撮っていると、子どもたちがさわらせてと集まってきました。とても柔らかな毛並みをみんなそっとなでてみます。
とても小さな目がわかりますか。トンネルは掘らず、落ち葉の下を歩いて昆虫やミミズを食べてます。体長9cm、尾長4cmでした。
写真を撮っていると、子どもたちがさわらせてと集まってきました。とても柔らかな毛並みをみんなそっとなでてみます。
レンゲソウ(ゲンゲ) 2011.4.22

野村町のあぜにきれいに咲いていました。以前は春の田んぼにたくさん見られたのですが少なくなりました。
マメ科植物は根に根粒菌が共生して、空気中の窒素を植物が利用できる窒素化合物に変えてくれます。レンゲソウは緑肥として
種子のできる前、花の咲いているときに土の中にすき込みますので、毎年種子を蒔く必要があります。
マメ科植物は根に根粒菌が共生して、空気中の窒素を植物が利用できる窒素化合物に変えてくれます。レンゲソウは緑肥として
種子のできる前、花の咲いているときに土の中にすき込みますので、毎年種子を蒔く必要があります。
タムシバ 2011.4.12

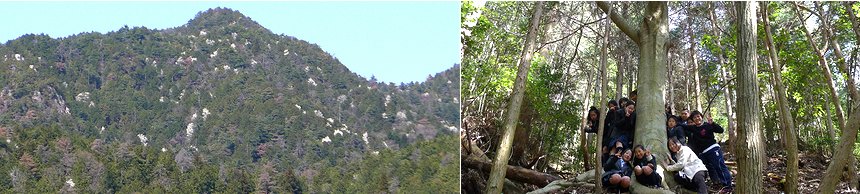
大原の山のあちこちに楽しみに待っていたタムシバが咲きました。昨年はなぜか とてもタムシバの花が少なくて心配していました。
でも今年はみごとに大原の春を彩っています。7年生といっしょに、学校の裏山に咲くタムシバの木に会いに行ってきました。
でも今年はみごとに大原の春を彩っています。7年生といっしょに、学校の裏山に咲くタムシバの木に会いに行ってきました。
スギナ(つくし) 2011.3.24

暖かくなった日をあびて、あぜ道につくしが出てきました。食べたことがないと答える子どもがほとんどです。ちょっと苦みのある
のが苦手なのかな。 胞子でふえるシダ植物です。胞子を飛ばし終えると、やがて土の中から光合成するための葉を伸ばしてきます。
のが苦手なのかな。 胞子でふえるシダ植物です。胞子を飛ばし終えると、やがて土の中から光合成するための葉を伸ばしてきます。
オオイヌノフグリ 2011.3.14

日本に昔からあったイヌノフグリと比べて、より大きな花を咲かせるのでこの名がつけられたそうです。明治時代にヨーロッパから
渡ってきた植物です。英名ではPersian speedwell(ペルシャのクワガタソウ)、Bird's-eye(小鳥の眼)です。 日本名も
この青くかわいい花にふさわしい名前がいいと思うのですが、昔の人のユーモアなのでしょう。
渡ってきた植物です。英名ではPersian speedwell(ペルシャのクワガタソウ)、Bird's-eye(小鳥の眼)です。 日本名も
この青くかわいい花にふさわしい名前がいいと思うのですが、昔の人のユーモアなのでしょう。
眠いのに 2011.3.7

啓蟄を過ぎてもまだ寒い日が続いています。運動場の砂場を掘っていたら出てきたと、冬眠からまだ目覚めていないトノサマガエルを
子どもたちから渡されてしまいました。このカエルくんは あとで安全な土のところに戻してやりました。
子どもたちから渡されてしまいました。このカエルくんは あとで安全な土のところに戻してやりました。
寒い朝 2011.2.16

今朝の気温は−4℃でした。立春を過ぎてもまだまだ寒い朝です。 野草たちはこの気温でも 凍りつかないようなしくみを
持っています。 ようやく朝日が霜に当たり始めました。これから暖かくなっていくでしょう。
持っています。 ようやく朝日が霜に当たり始めました。これから暖かくなっていくでしょう。
ニホンザル 2011.1.24

学校の裏に現れたニホンザルです。雪でエサが少なくなって里へ下りてきたのでしょう。校舎の向かい側の家の屋根に上がりました。
サルたちも生活がたいへんなのでしょうが、作物に被害をおよぼさないように帰ってもらえないかな。
サルたちも生活がたいへんなのでしょうが、作物に被害をおよぼさないように帰ってもらえないかな。
ルリビタキ 2011.1.18

大雪の日に、車のサイドミラーに止まっていたルリビタキの雌です。雄は背中とつばさが青色ですが、雌は落ち着いたカーキ色です。
 尾の青色とからだの脇のミカン色でちょっとおしゃれです。
尾の青色とからだの脇のミカン色でちょっとおしゃれです。
雪の日にはえさを探すのがたいへんだと思います。凍てつく冬を乗り越えていく力が この小さな体のどこにあるのでしょう。
夏には亜高山帯の林で毛虫やクモをたくさん食べてくれていて、冬には大原のような盆地にも下りてきます。
ヒタキの名は 地鳴きがヒッヒッ、またはカッカッと聞こえる火打ち石を打つ音に似ているからです。
 尾の青色とからだの脇のミカン色でちょっとおしゃれです。
尾の青色とからだの脇のミカン色でちょっとおしゃれです。雪の日にはえさを探すのがたいへんだと思います。凍てつく冬を乗り越えていく力が この小さな体のどこにあるのでしょう。
夏には亜高山帯の林で毛虫やクモをたくさん食べてくれていて、冬には大原のような盆地にも下りてきます。
ヒタキの名は 地鳴きがヒッヒッ、またはカッカッと聞こえる火打ち石を打つ音に似ているからです。


