エノコログサ 2009.12.10

収穫の終わった田んぼのあぜに、すっかり枯れたエノコログサが冬の日ざしを受けて輝いていました。
オオカマキリ 2009.10.27

運動場のそばで 子どもたちに見つかったオオカマキリのつがいです。大きいほうがおかあさんカマキリです。
子どもたちはカマキリの扱いも心得ていて、じょうずに手の上に乗せて見せてくれました。
子どもたちはカマキリの扱いも心得ていて、じょうずに手の上に乗せて見せてくれました。
冬眠まえに 2009.10.20

畑を掘り返したときに、土の中から出てきたトノサマガエルです。薄い皮だけではもう寒くなったので、そろそろ冬眠し
始めていたのを起こしてしまったようです。夏の間、野菜を食べる昆虫を退治してくれていたので、大切にしたい仲間です。
始めていたのを起こしてしまったようです。夏の間、野菜を食べる昆虫を退治してくれていたので、大切にしたい仲間です。
キンエノコロ 2009.10.14

エノコログサの仲間ですが、のぎ(芒)が光を透すと金色に輝きます。たくさん生えていたのは乙ヶ森の前に広がる畑のあぜです。
ヒガンバナ 2009.9.24

大原にヒガンバナがたくさん咲きました。球根に毒を持っているので、たんぼのあぜにネズミが穴を開けることが防げるそうです。
あぜに穴が開くと水田に 張ってあった水が抜けてしまいます。
そのために稲の栽培技術のひとつとして、中国から球根が持って来られたのでしょう。
あぜに穴が開くと水田に 張ってあった水が抜けてしまいます。
そのために稲の栽培技術のひとつとして、中国から球根が持って来られたのでしょう。
トノサマガエル 2009.9.17

畑で見つけたトノサマガエルです。農薬を使わない畑をパトロールして 昆虫を食べてくれているありがたい存在です。
キマワリ 2009.9.1

校門前の歩道で昆虫大好きな3年生が捕えたキマワリです。ゴミムシダマシの仲間でクヌギなどの朽木を食べてます。
手の上でもよく歩き回って おとなしくしていません。
手の上でもよく歩き回って おとなしくしていません。
ヘビトンボ 2009.8.26

ヘビトンボの成虫が渡り廊下にいました。大型のカゲロウです。夏の水生昆虫調査のときには川底にいる幼虫をよく見かけます。
大型の幼虫は強いあごを使って 他の水生昆虫を食べています。幼虫は「孫太郎虫」とも呼ばれています。
大型の幼虫は強いあごを使って 他の水生昆虫を食べています。幼虫は「孫太郎虫」とも呼ばれています。
ツマグロヒョウモン 2009.7.10

玄関のパンジーに卵を産みに来ていたツマグロヒョウモンです。教室でも飛び立たず、子どもたちの肩や手に乗ったまま 逃げていきません。
アオハダトンボ 2009.6.27

大原を流れる高野川の探査にいきました。ヨシにおおわれた自然の護岸にアオハダトンボがいっぱいいました
きれいな流れの川にしか見られないアオハダトンボです。高野川は川幅は2mもないところもあり、そんなところには
ヒトがまったく入り込んでいない自然が残されています。
きれいな流れの川にしか見られないアオハダトンボです。高野川は川幅は2mもないところもあり、そんなところには
ヒトがまったく入り込んでいない自然が残されています。
モリアオガエル 2009.6.1

校門のところで、下校する子どもたちに見つかってしまったモリアオガエルくんです。
背中の斑点模様はいろいろあって、まったく模様のないのもいるのです。これから田んぼの縁へ、泡に包まれた卵を産みに
行くところだったのでしょうか。
背中の斑点模様はいろいろあって、まったく模様のないのもいるのです。これから田んぼの縁へ、泡に包まれた卵を産みに
行くところだったのでしょうか。
ニホンジカ 2009.5.29

高野川の河原を歩いていたニホンジカです。大原でも 作物へのイノシシやシカの食害で困っています。
ほんとうはシカたちのほうが先住民です。ヒトが農業のために後から入ってきたのですが、共に生きていける方法を考えたいものです。
ほんとうはシカたちのほうが先住民です。ヒトが農業のために後から入ってきたのですが、共に生きていける方法を考えたいものです。
こん虫さいしゅう 2009.5.21

3年生といっしょに採集にいきました。アリのからだについて調べたので、他の昆虫のあしの数を見てみようと出かけました。
昆虫がいっぱい見られる豊かな自然に囲まれていることの幸せを、こどものときに経験しておくことは大切です。
3年生のこどもたちはモンシロチョウ、キアゲハ、ツマグロヒョウモンなどいろんな幼虫をあちこちからたくさん集めてきてくれています。
昆虫がいっぱい見られる豊かな自然に囲まれていることの幸せを、こどものときに経験しておくことは大切です。
3年生のこどもたちはモンシロチョウ、キアゲハ、ツマグロヒョウモンなどいろんな幼虫をあちこちからたくさん集めてきてくれています。
ヤモリ 2009.5.13

かわいいヤモリを捕まえたと見せにきてくれました。6年生の手の中に握られていたのは、まだ子どものニホンヤモリです。
変温動物であるハ虫類は夜に活動することはめずらしいのです。ヤモリはハエや蛾などの昆虫を食べるので大切にされています。
変温動物であるハ虫類は夜に活動することはめずらしいのです。ヤモリはハエや蛾などの昆虫を食べるので大切にされています。
カエデの花 2009.5.2

校門前のカエデ(もみじ)に花が咲いていました。ここにミツバチが蜜を集めに来ていました。
この花が終わると、やがてプロペラのようなかたちの赤い種子ができます。
この花が終わると、やがてプロペラのようなかたちの赤い種子ができます。
ヤマブキ 2009.4.23

和田橋の近くに咲いているヤマブキです。園芸種の八重の花には種子ができませんが、一重のヤマブキは種子ができます。
山吹色は美しい日本の色のひとつです。川沿いのこのあたりにはシャガの花もたくさん咲いています。
「なヽへ八重 花は咲けども 山吹の みのひとつだに なきぞあやしき(かなしき)」 兼明親王 後拾遺
山吹色は美しい日本の色のひとつです。川沿いのこのあたりにはシャガの花もたくさん咲いています。
「なヽへ八重 花は咲けども 山吹の みのひとつだに なきぞあやしき(かなしき)」 兼明親王 後拾遺
キジ 2009.4.15

通勤途中に2羽の雄キジに出会いました。それぞれ井手町と草生町の畑です。大原の畑では、キジが歩いているのをしばしば見かけます。
農家のひとたちにも守られているのでしょう。「ケンケーン」または「ゲンゲーン」と縄張り宣言をする雄の声もよく聞きます。
人を気にしないようですが、私がカメラを取り出そうとするとスタスタと向こうへ去ってしまい、写真に撮られるのをいやがりました。
農家のひとたちにも守られているのでしょう。「ケンケーン」または「ゲンゲーン」と縄張り宣言をする雄の声もよく聞きます。
人を気にしないようですが、私がカメラを取り出そうとするとスタスタと向こうへ去ってしまい、写真に撮られるのをいやがりました。
ワサビ 2009.4.9

山岳部員とひとの歩かないルートから山を下りてきたとき、山のふもとの森の中にワサビの花が静かに咲いていました。
渓流の冷たい水辺に生えていることがふつうです。ここではヒノキの下草のように広がっていました。
アブラナ科の仲間なので4枚の花弁を持っています。
渓流の冷たい水辺に生えていることがふつうです。ここではヒノキの下草のように広がっていました。
アブラナ科の仲間なので4枚の花弁を持っています。
タムシバ 2009.4.7


大原の春を彩るタムシバです。周りの山々にあちこち白く花が見えています。近づいて見るためには道のない藪の急斜面を
登らないと出会えません。 学校の裏山に見えるタムシバの大木に今年も会いにいきました。
登らないと出会えません。 学校の裏山に見えるタムシバの大木に今年も会いにいきました。
ナズナ 2009.3.27

耕されるまでの春の畑に咲いているナズナです。正月七日の七草がゆにも使います。
種子の形が三味線の三角のばちの形に似ているので、ぺんぺん草とも呼ばれます。
種子の形が三味線の三角のばちの形に似ているので、ぺんぺん草とも呼ばれます。
ヤマガラ 2009.3.18

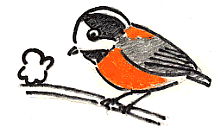 咲き始めたサクラにヤマガラが来ていました。黒とオレンジ色でヤマガラとすぐわかります。
咲き始めたサクラにヤマガラが来ていました。黒とオレンジ色でヤマガラとすぐわかります。鳴き声は鼻にかかったような「ニーニー」と「ツツビー、ツツビー」と聞こえます。
天神さんの縁日などで おみくじを引く芸を見せていたのは、樹木につく虫をつついて食べる行動を持っているからです。
つぼみふくらむ 2009.3.3

校門そばにある八重のサクラは例年早く咲き出します。ソメイヨシノが咲きはじめる頃には散ってしまうくらいです。
つぼみもふくらんで今年はとくに早く咲きそうです。卒業式に咲いているかもしれません。
つぼみもふくらんで今年はとくに早く咲きそうです。卒業式に咲いているかもしれません。
ノウサギ 2009.2.10

美濃瀬橋のところで車にはねられてしまったノウサギくん。夜に活動したときに、きっと飛び出してしまったのでしょう。
ピーターラピッドのかわいい目をしています。体長45cm、体重2.9kgのおとうさんです。
ピーターラピッドのかわいい目をしています。体長45cm、体重2.9kgのおとうさんです。
ホソウリゴケ 2009.1.22

校門前の石垣です。最近は氷点下の気温のときも多いのに、凍らずに春を待っています。この季節にも緑色があざやかです。
コンクリートや石垣のすきまに生えているのをよく見かけるコケです。
コンクリートや石垣のすきまに生えているのをよく見かけるコケです。
カキ 2009.1.5

草生町、乙ヶ森のところにあるカキです。栽培種ではなく野生の柿の木でしょう。
熟すまでカキが渋いのは、種子がしっかりできるまで動物に食べられないように。タマネギがけものに毒であったり、
ダイコンに辛みがあるのも動物から身を守る手段です。
熟すまでカキが渋いのは、種子がしっかりできるまで動物に食べられないように。タマネギがけものに毒であったり、
ダイコンに辛みがあるのも動物から身を守る手段です。


