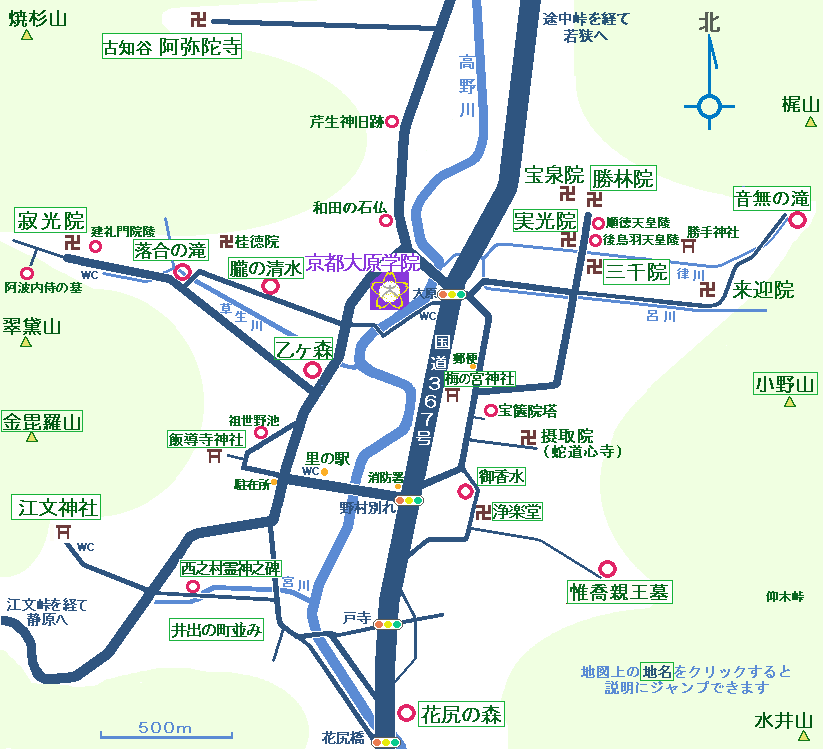古知谷 阿弥陀寺 (こちだに あみだじ)
木喰上人弾誓が開創した浄土宗の寺院。阿弥陀如来坐像は重要文化財。
境内は紅葉の名所として知られる。樹齢800年以上の古知谷カエデは京都市の天然記念物に指定されている。
[ 弾誓上人は尾張国あまべの里に出生し、幼名を弥釈丸と号す、九歳の時出家し、美濃国塚尾の観音に百日参籠し、念仏諸行に勝るゝ霊文をさづかり。
五条の橋を通り給うとき、洛北のかたに紫雲空に靉靆
(あいたい)、光明赫々としたる所あり、これを慕ふて遂に此所に至り、是ぞ有縁の霊地となりとて、則一宇の堂舎を建立しけり。其時頭に雪をいただきたる老翁、阿弥陀仏一体持来り、本尊にし給へと上人にあたへ、忽然として行方なし。] 都名所図会
御杖水(おつえのみず)
[ 阿弥陀寺 はじめは水乏しければ、
(弾誓)上人 鉄杖を以て、岩間を穿ち給へば、流れ瀧の如し、服すれば病苦を免るゝもの多し。] 都名所図会


寂光院 (じゃっこういん)
聖徳太子が用明天皇の菩提を弔うために建立されたと伝えられている。
また、平清盛の娘であり、安徳天皇の母である平徳子が、平家滅亡後29歳の若さで出家し 建礼門院徳子として平家一門の菩提を弔った尼寺。
[ 建礼門院と申は、平相国清盛公の御女にして、十五歳にて女御の宣旨を蒙り、十六にて更衣のくらゐにそなはり、廿二の御時皇子御誕生ある、是を安徳天皇と申奉る。平家の一門西海にて入水の時、やうやう源氏の武士にたすけられ、ふたゝび洛へかへり給ひ、初は東山の麓吉田の辺に住せ給ひ、廿九の御時かしらをおろし、さまをかへさせられ、文治元年長月の末に此寂光院へ入らせおはします。] 都名所図会
「おもひきや深山の奥にすまゐして 雲ゐの月をよそに見むとは」 建礼門院 平家物語
「かしかまし大原の野の轡虫手綱ひかえて法の声きけ」 建礼門院
[ 此御詠より此草生村には 今もくつは虫鳴ずとなん] 都名所図会
平家物語では、建礼門院を訪ねて来られた後白河法皇の大原御幸(おおはらごこう)の記述がある。
「池水に汀
(みぎわ)のさくら散りしきて 浪の花こそさかりなりけれ」 後白河法皇 平家物語


落合の滝 (おちあいのたき)
草生町の寂光院への道のすぐ脇にある小さな滝。ふたつの小川が合わさるところにある。
「ころころと小石流るる谷川の かじかなくなる落合の滝」 建礼門院

朧の清水 (おぼろのしみず)
今も冷たい水がわき出ている小さな泉。ぜひ月を映して見たい。歌枕として 平安時代からたくさんの歌に詠まれてきた。寂光院に隠棲した建礼門院も親しんだ。
[ むかしより名高きしみづにして、和歌に詠ずる事数多し。つねに湛々として、月の影は清水にやどりて澄、しみづは又月の皎なるをうつして清く。] 都名所図会
「そよ 大原やおぼろのしみづ世にすまば 又もあひみんおもがはりすな」 後白河法皇撰 梁塵秘抄
「すみなれし おぼろの清水せく塵を かきながすにぞ すゑはひきける」 西行法師 聞書集、往生要集
「ひとりすむ おぼろの清水友とては 月をぞすます大原の里」 寂然法師 山家集
「程へてや 月も うかばん大原や おぼろの清水すむなばかりに」 良暹法師 後拾遺集
「水草ゐし 朧の清水底澄て こゝろに月の 影はうかぶや」 素意法師 後拾遺集
「入る月の朧の清水いかにして 遂に澄むべき影をとむらん」 順徳院 続古今集
「わが恋は朧の清水岩越て せきやるかたもなきこころ哉」 俊頼
「大原や いづれ朧の清水とも 知られず秋は すめる月かな」 兼好法師
「春雨の 中におぼろの 清水かな」 与謝蕪村

飯導寺神社(はんどうじ じんじゃ)
野村町の鎮守の森で農耕神の飯導大権現を祀る。「はんどじさん」とも呼ばれる。
境内には、相撲が奉納された土俵が残っている。

良暹山荘(りょうぜんさんそう)
比叡山の天台僧であった良暹
(りょうぜん)法師がこの近くの良暹山に隠棲したとされているが、どこにあったかは不明。
「さびしさに 宿をたち出でて ながむれば いづくも同じ 秋の夕暮れ」 良暹法師 後拾遺集
「山里の甲斐もあるかな時鳥 ことしもまたで初音きゝつる」 良暹法師 後拾遺集
[ 大原にあるよし袋草子に見へたり。旧地詳ならず] 拾遺都名所図会
[ 清輔袋草子曰、人々大原に遊行す。おのおの騎馬しけるに、俊頼朝臣ひとり俄に下馬しけり。人々驚いてこれを問しむるに。答て曰、此所良暹が旧房なり、何んぞ下馬せざらんや。人々これをきゝて大に感歎し、皆下馬して行過ぬ。] 拾遺都名所図会
祖世野池(そよのいけ)・真守鉄盤石(さねもり かなとこいし)

池の名がついているが、今は小さな泉である。
三条小鍛冶宗近が使った小鍛冶の水ともいう。
左手前には、刀を鍛えたという平らな鉄盤石がある。
[ 草生村の東 野村の内、北の方山下にあり。伝云、此所鍛冶真守が居宅なり、大原真守といふ名鍛冶これなり] 拾遺都名所図会
和田の石仏 (わだのせきぶつ)
樫の木の木陰におられる和田のお地蔵さん。
もとは三千院の翁地蔵の傍におられたが、その翁地蔵とけんかして 耳をかみ切って勝ち、ここへやって来られたという。

実光院 (じっこういん)
天台声明を伝承するために建立された寺のひとつである。
律川の水を取り入れ、池の手前を俗世間、向こう側を仏の浄土に見立てた池泉観賞式の庭園と、茶室のある池泉回遊式の庭園の2つがある。


勝林院 (しょうりんいん)
古くから来迎院とともに天台声明の道場であった。
平家滅亡の翌年(1186年)ここ勝林院で、浄土思想をめぐり 法然と他宗派が大原問答を行った。
律川に架かる赤い茅穂橋のそばには、熊谷蓮生坊が法然上人を守るために持っていた鉈
(なた)を捨てさせた「鉈捨藪」の石碑がある。
大原女行列の出発点を寂光院と1年ごとに交代する。
鉈捨藪 (なたすてやぶ)
[ 大原問答のとき、熊谷蓮生師 鉈を袖に隠して法然上人に供す、蓮生のいはく師もし対論に負給はば、法敵を討殺さんとの用意なりと、師これを聞て大に制し給へば、鉈を此ところにすて置しとなり] 都名所図会
熊谷腰掛石(くまがいこしかけいし)
[ 律川の橋南のつめにあり、蓮生法師 此所に腰をかけて、法問の勝劣を聴聞しけるなり ] 都名所図会
法然上人腰掛石(ほうねんしょうにんこしかけいし)
[
(羅漢橋)同所西にあり、伝云、上人勝林院本尊に参詣の時は、かならず此石上にやすらひ給ふとなん ] 拾遺都名所図会


来迎院 (らいごういん)
慈覚大師円仁が中国天台山を模して開山した。聖応大師良忍が1109年建立。
薬師如来、弥陀如来、釈迦如来像は重文。
獅子飛石 (ししとびいし)
来迎院本堂の横にある。良忍上人が声明を唱え修行中に、この石が獅子となって堂内を駆けめぐり吠え回ったという。
呂律川 (りょりつのかわ)・ 呂川と律川
[ 音無の瀧川なり、南北に別れて、南を呂川(りょせん)といひ、北を律川(りつせん)となづく。漢土の魚山に瀧川二流あり、呂律川といふ、其例によるなり] 都名所図会
音無の滝 (おとなしのたき)
天台声明や融通念仏宗をおこした 良忍上人の声明が滝の音律に同調して音が消えて無くなったと言われ、この滝を「音無」と名付けた。律川の上流にあり、三千院手前の山道を東へ20分ほど登ったところ。
[ 音無瀧は来迎院の東四町にあり、飛泉二丈余にして翠岩に添ふて南へ落る、蒼樹蓊欝として陰涼こゝろに徹し、毛骨悚然として近きがたし ] 都名所図会
「音なしの滝とは聞けども昔より 世に声高き大原の滝」 西行法師
「小野川のうへより落つる瀧の名の 音なしにのみ 濡るゝ袖かな」 西行法師 夫木集
「恋ひわびて ひとりふせやに 夜もすがら 落つる涙や 音無の滝」 藤原俊忠 詞花集
「朝夕に泣くねを立つる小野山は 絶えぬ涙や音無の瀧」 紫式部 源氏物語・夕霧の巻

古文書「北肉魚山行記」では、もっと奥に規模の大きな本当の音無滝があると書かれている。これが現在のどの滝のことを指しているのかわからない。一の滝が現在の「音無滝」と呼ばれているもので、さらに上流に二の滝と三の滝がある。
(山岳部ページ)
小野山(おのやま)
もとは梶山・小野山などの大原の東側にある山の連なり全体を指していた。この地にいた豪族、小野氏のかかわりがあるのだろう。
音無の滝と共に和歌によく詠まれた地名であり、かつては炭焼きの里としても知られていた。
「ふる雪もをやめやをやめ小野山に 椎柴かるはしばしばかりぞ」 源顕仲 永久百首
「都にも初雪ふれば小野山の まきの炭竈
(すみがま)たきまさるらむ」 相模 後拾遺集
「雪わけて外山をいでしここちして 卯の花しげき小野のほそみち」 西行法師 山家集
「都近き小野大原を思ひ出づる 柴の煙のあはれなるかな」 西行法師 山家集
「よそにてもさびしとはしれ大原や 煙をたへぬ炭がまのさと」 土御門院 新続古今
「炭がまの煙の里の名にたてゝよそにもしるきをのゝ山下」 藤原伊定 新続古今

江文神社 (えぶみじんじゃ)
江文神社は大原八ヶ町の総氏神。倉稲魂命
(ウガノミタマノミコト)が祀られている。
古くから江文山(金毘羅山) の頂上の朝日の一番早く登るところに祀られていた神々を、
平安時代の後期に 里人がふもとに御殿を創建したと伝えられている。
「昔、井出の大淵に大蛇がいて、おりおり里に出て 人を捕り食らうので江文神社に集まって隠れた。」といわれているのは、川の氾濫による避難のことであろうと思われる。



9月1日にはそれぞれの町の提灯を掲げて集結し、道念踊りがおこなわれる。(八朔踊り)

金毘羅山(こんぴらさん)
古くは江文山と呼ばれ、火壷・風壷・雨壷があり、雨乞い祈願が行われたとのこと。また、この山は平安京の東北の鬼門に当たるとされた。
火壷(ひつぼ)、雨壷(あまつぼ)、風壷(かぜつぼ) 〔 井出村江文社の後山にあり。山間に自然の三窟にして石の蓋あり、旱の時雨壷に向ふて雨を祷るに感応あり。此地魔所なりとて土人怖れをなすなり 〕 拾遺都名所図会
後年、山の中腹に金比羅大明神と崇徳天皇を祀る琴平神社がつくられた。これは四国に流された崇徳天皇が金毘羅神を崇敬していたためである。
山の東面には岩場が点在し、ロッククライミング練習のゲレンデでもある。
雨乞い
大原の雨乞い行事は大正末期に行われたのが最後らしい。その年は田植えの六月を迎えても雨が降らないので、各村から選ばれた五名、計四十名の男たちが晴天の中を蓑・笠をつけて太鼓と鉦をたたき、「雨ごいのズンゴイノ、雨たもれズンゴイノ」と はやしながら金毘羅山に登り、「雨つぼ」を開けて帰ってきたそうである。 帰りの道にはもうすでに大雨となって、次の日から田植えが始まったということである。
その年は豊作であったのに違いない。秋にはそのお礼まいりをした。 各村から選ばれた十数名の稚児が花笠を被って江文神社拝殿で、高張提灯に照らされて花笠踊りを奉納したと伝えられている。

おつう伝説
「昔、大原の里におつうという娘が住んでいた。ある日、若狭の殿さまに見初められ、女中として若狭で暮らしたが、病に伏すと殿様の熱も冷め、里に戻された。おつうは悲しみのあまり、大原川(高野川)の女郎淵に身を投げると、おつうは大蛇となった。 そしてある日、殿様の行列が花尻橋を通りかかったところを襲った。荒れ狂う大蛇は家来に切り殺された。すると その夜から激しい雷雨や悲鳴に見舞われた。 恐れおののいた村人たちは大蛇の頭を
乙が森に、胴は
西之村霊神之碑のところに、尾は
花尻の森に埋めて、霊を鎮め供養した。その後、大原の里にかかる朝もや(小野がすみ)は大蛇の姿にたなびくといわれている。」
乙が森 (おつがもり)

西之村霊神之碑 (にしのむられいじんのひ)

花尻の森 (はなじりのもり)
波那志里の杜(はなじりのもり)と書き記すのが元であったらしい。
猿田彦神を祀った小野源太夫社と称する小社があって、江文神社の御旅所となっていて 一の鳥居がある。
ここにはツバキの古木がたくさん見られる。
源太夫社
[ 杜の中にあり、江文の末社なり。此社の北に江文の一鳥居あり ] 拾遺都名所図会


小野霞 (おのがすみ)
雨のやんだ冬の朝など、大原を囲む山の中腹を白い大蛇のように伸びる層雲を小野霞と呼んでいる。

井出の町並み (いでのまちなみ)
川の氾濫に備えた、しっかりした古い石垣と旧家の町並みが いまも残っている。戦国武将が宿泊に使ったという旧家がある。


惟喬親王(これたかしんのう)旧跡
文徳天皇の第一皇子。
大宰帥・弾正尹・常陸太守・上野太守などを歴任したが、二十九歳で出家したあと この地に隠棲した。
[ 上野の村南の方田の字に御所の内といふあり、伝云、惟喬親王閑居の所なりとぞ。又同所ひがしの山際に一本杉といふ所あり、其地に古き石塔あり、土人云、惟喬親王の御墓なりと云伝ふ] 拾遺都名所図会
これたかのみこのもとにさしかり かよひけるを、かしらおろして をの
(小野)といふ所に侍りけるに、正月にとぶらはんとてまかりたりけるに、ひえの山の麓なりければ、雪いとふかゝりけり、しゐてかの室にまかりいたりて、
「忘れては夢かとぞ思ふ思ひきや 雪ふみわけて君を見んとは」 在原業平 古今集
「白雲の絶えずたなびく嶺だにも 住めば住みぬる 世にこそありけれ」 惟喬親王 古今集
「桜花散らばちらなむ散らずとて ふるさと人の来ても見なくに」 惟喬親王 古今集
「夢かともなにか思はむ憂き世をば そむかざりけむ程ぞくやしき」 惟喬親王 新古今集

御香水 (おこうすい)
「昔々、里を荒らす白狐に困り みんなで狐狩りをすることになった。ところが、白狐は上野村の吉兵衛さんのかまどの中に隠れて捕まらなかった。
その夜、吉兵衛さんの夢に白狐が恩返しに現れ、屋敷のうしとら(北東)の方角を掘れば清水が湧き出て霊薬になると教えてくれたのです。そこを掘ってみると、きれいな清水が湧いてきたそうです。」
この泉は病気に効くそうですが ふだんは湧かず、毎年一回、旧暦の六月十六日にだけ出るということです。

浄楽堂(じょうらくどう)
昔はこの近くに惟喬親王のお寺が36あったが火災で焼け、残った仏様ををここへお奉りした。十一面観音、地蔵菩薩、阿弥陀如来がおられる。
ここでは、成人の日にお碗に盛られたサイコロ状の大根を転がし、これを全員が繰り返す「おこない」と、篠竹の的に向かって矢を射る「お弓」が氏子によって行われる。

梅の宮神社(うめのみや じんじゃ)
江文神社の境外摂社で、木花咲耶姫を祀る。 境内には大きな榧ノ木とカツラの木がある。
本校はここ梅の宮神社の東側に接したところに、大原校として明治八年五月二十八日創立された。

龍女山摂取院(りゅうにょさん せっしゅいん)
蛇道心寺という、浄土宗の寺院。聖徳太子の作と伝えられる本尊阿弥陀仏がある。
開基 浄住法師 〔 此法師俗人たりし時、専ら色欲を好み、妻の妹に密通しぬ。妻これを嫉といへども制するに力なし、終に苦悩して死す。其怨霊たちまち小蛇となつて夫が首に纒ふ、取すて殺せども寝中に現じて又もとのごとし。こゝに於て罪業の深きを悟つて、剃髪染衣の身となり、此地に蟄居して、もつぱら念仏を修す。されども蛇は常に首を去ず、いよく自障懺悔しぬれば、老年におよんで蛇首を脱して成仏すと夢見る。これ滅罪歓喜して、益念仏怠らず、往生素懐を遂にける。已上縁起の大意 〕 拾遺都名所図会
宝篋院塔 (ほうきょういんとう)
大長瀬町公民館のそば。 右側のが古く、鎌倉時代のものだそうだ。元亨元年(1321)建立という刻印がある。
左側の塔は南北朝時代の作といわれる。 右手前におられるのは不動尊。このところに墓地があったそうです。

Text and photograph Copyright © 2003-2025 Keiji K.



↑